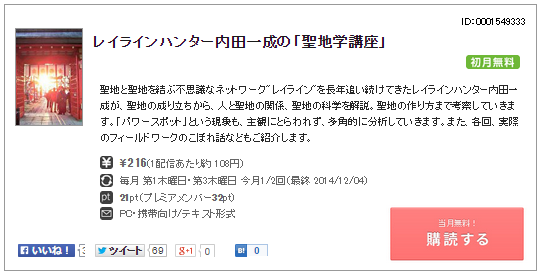世界では、COVID-19がますます猖獗を極め、日本でも非常事態宣言の再発動が取り沙汰される今、過去に深刻なパンデミックに見舞われた人類は、どのような混乱に見舞われ、それにどう対処し、パンデミックによって何が失われ、そして何が生まれたのか振り返ってみました。
この稿は、2020年3月に配信したものです。
---------------------------------------------------------------
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
レイラインハンター内田一成の「聖地学講座」
vol.186
2020年3月19日号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
○パンデミックが告げるコト
・鞭打ち苦行とコペルニクス
・革新と反動
◯お知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パンデミックが告げるコト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の新型コロナウイルスの広がりは、ついにWHOがパンデミックを宣言し、世界全体が閉鎖状態になるまでに発展してしまいました。とくにヨーロッパでは、恐ろしいほどに緊張感が高まっています。
日本もこれからどう推移するかまったく予想がつきませんが、今のヨーロッパの対応はエキセントリックとも思えるほどです。しかし、それは中世にヨーロッパが経験したペストによるパンデミックを考えれば、当然の反応ともいえます。
14世紀半ばから15世紀半ばにかけての最初の大流行では、イギリスやイタリアでは、人口の80%が死亡して文字通りゴーストタウンと化した都市だらけで、ヨーロッパ全体で見ると人口の30から60%が失われたと推定されています。
この流行は猖獗を極めた後に収束しましたが、再び、17世紀から18世紀にかけて襲いかかります。イタリアのミラノでは、当初は事態を軽く見ていて、恒例のカーニバルが実施されました。ところが、これが仇となり、カーニバルがクラスターとなって、イタリア全土に一気に広がってしまいました。ピーク時には一日に3500人が死亡するという惨事になりました。さらにヨーロッパ各国に飛び火して、ロンドンだけでも死者7万人、フランスのマルセイユでも5万人が亡くなりました。
最近よく目にする不気味な絵、鳥の嘴のようなマスクをつけて体全体を厚い布のコートで覆った人物の姿は、この時代のペスト患者の治療にあたった医師の防護服姿です。
今回、新型コロナウイルスのパンデミックに直面したヨーロッパでは、中世に世界を滅亡の瀬戸際まで追い込んだペストの記憶が生々しく蘇っているのです。
ところで、この「パンデミック」という言葉は、ギリシア語の"pandemia(パンデミア)"、"pan(全て)+ demos(人々)"に由来します。panには、牧神という意味もあり、これは羊飼いの神であると同時に全ての自然を象徴する神でもありました。
牧神(パン)は、森の中で静かに昼寝をしているときに、人間にその眠りを妨げられ、その仕返しに、森の中に一人でいる人間の前に突然現れてその者を恐怖に陥れたとされます。このパンに取り憑かれた状態が「パニック」です。
キリスト教では、異教の神である牧神は制圧されるべきものとされ、キリストが十字架に架けられて昇天したときに自然を支配していた牧神を滅ぼしてこれに入れ替わったとされます。キリストの磔刑はキリストの神格化の象徴であり、全能の神とその僕たるキリストの名のもとに、自然を支配するという宣言だったわけです。
最初のペストのパンデミックでは、ポーランドだけがたいした被害を受けませんでした。それは、ポーランドではアルコール度数の高い蒸留酒で食器や家具を消毒したり、体を拭く習慣が定着していたこと、それに、国土の多くがまだ農地化されずに原生林のまま残り、そこにネズミを食べるオオカミや猛禽類などが多く生息していたからだといわれます。
自然霊である牧神を滅ぼし、自然を制圧した都市ではペストが猖獗を極め、牧神がまだ生き残っていたポーランドのようなところではペストから守られた。それは、現代にも活かすべき大切な教訓を物語っているように思えます。
過去、世界がパンデミックに晒されたとき、何が起こったのかを振り返って見ること、それは、今、私たちが置かれている状況を客観的に見つめることになります。パニックに陥らず、冷静に、社会がこの事態をどう乗り越えていけばいいのか、さらに、パンデミック後の社会はどのようなものであるべきなのか、それを乗り越えた先で、どのような社会を構築していけばいいのかを考える上で、必要なことだと思います。
●鞭打ち苦行とコペルニクス●
過去にパンデミックに襲われた社会は、否応なく大きな社会変動を経験することになりました。今回のパンデミックでも、経済活動が麻痺して、リーマンショックが霞むほどの経済危機を経験することになると予想されています。当然、これまでの経済成長重視の価値観そのものを見直す機運も高まるでしょう。
ところが、先がまったく見えない今の状況下では、人の反応は革新と反動の両極に分かれています。
一方では最先端の技術を駆使して、この新種のウイルスの毒性や感染メカニズムを解明して、ワクチンを急ピッチで開発していこうという取り組みと、それを冷静に見守る姿勢。さらに、ITをフルに活用して、感染の様子を可視化し、データを公開・共有することでこれ以上の広がりを食い止めようという試みがスピーディに実践されています。
そして、一方では、デマに踊らされてパニックに陥り、買いだめに走ったり、恐怖に発する怒りを外国人に向けるレイシズムが起こったり、さらには宗教や根拠のない信仰に縋って、まじないや託宣を信じ込んだり、終末論や陰謀論を叫んだり、あるいは考えることを放棄していわれのない楽観主義に浸ったりといった反動、反理性的な方向に向かってしまう人たちがいます。。
面白いことに、というか人間の本質は変わらないといったほうがいいのか、こうした二極化は、過去にもまったく同じ傾向が見られました。
ヨーロッパが何度もペストに襲われた中世には、封建的で陰鬱な「暗黒時代」というイメージがつきまとっています。実際、異端審問や魔女裁判などの陰惨な迫害が長く続き、恐怖と不安に覆われていました。しかし、一方では、ルネサンスが着実に進行した時代でもありました。
最初のペストの猖獗の記憶もまだ生々しかった1524年の秋、占星術師たちは、惑星が魚座の位置を占めて「大変動の時代」に入り、再び世界は恐怖に包まれると予言します。そして不安と恐怖が支配する「魚座の時代」をテーマにした膨大な数のテキストが印刷され、流布されてゆきます。そうしたテキストには、不気味な占星術の予言とあわせて、世界の終末を説くヨハネの黙示録の言葉が、恐怖を煽るスパイスとして散りばめられていました。
それを発端に、社会不安が広がり、各地でパニックが起こります。そんな中から、「鞭打ち苦行者の兄弟団」という一種の社会運動が沸き起こります。彼らは、疫病や飢饉は驕り高ぶった人間に対する神の怒りであると信じ、神の罰が下る前に自らを罰することで神の怒りを鎮めようと考えたのでした。
この苦行者たちは、隊列を組んで街の広場へと入り、そこで円陣を組んで、リズムをとりながら自分の背中や胸を打ち始めます。革紐に鉄釘を付けた重い鞭が皮膚に喰い込み、彼らの体はたちまち血まみれになります。さらに、激励役の苦行者が何人か円陣の中央に立ってこの鞭打ちを指揮し、みなをより激しい苦痛へと誘なっていきます。
苦行者たちは、賛美歌を歌いながらむち打ちのペースを早め、自らの血で濡れた地べたに身を投げだし、のたうち回りながらさらに激しく自らに鞭を加え、自己懲罰の陶酔へと入っていきます。彼らを取り巻いて眺めていた街の住人たちは、どんどんエスカレートしていくその苦行に衝撃を受け、すすり泣きながら神に贖罪を祈りました。
この苦行者の集団が街を巡るうちに、仕事も家庭も投げうってこの集団に参加する人間が雪だるま式に増えてゆきました。それは、巨大な集団狂気でした。
鞭打ち苦行に人を駆り立てたのは「恐怖」でした。占星術によって惹起されたペストの猖獗が再び迫りくるといういいしれない恐怖が、彼らを狂気へと駆り立てたのです。
こうしたいいしれない恐怖への闇雲な反応は、他にも様々な奇妙な発想を生み出しました。中でもおぞましかったのは「血の信仰」です。それは、絞首刑に処せられた罪人の血を飲めば、らい病(ハンセンシ病)が治るというものでした。
らい病もまた、その症状の悲惨さから恐怖をかき立てた病でした。これも恐怖の源泉の一つである犯罪者を囚え、処刑することは、一つの恐怖を収束させることであり、恐怖の制圧でした。罪人の血は、制圧された恐怖の象徴であり、これを飲めば、自らに巣食った恐怖の源であるらい病も制圧できると考えたわけです。
皮肉なことに、これは、無毒化したウイルスを体に取り入れることで免疫を獲得する「ワクチン療法」と奇妙にシンクロする発想でした。もちろん、罪人の血を飲んでも効果があるはずはなく、ときにはそれが死につながったり、新たな病の原因にもなったのですが。
「祝祭日」(gala day)という言葉がありますが、これは「処刑の日」(gallows day)に由来します。群衆が晴れ着を着て、罪人が首を切り落とされたり絞首されたりするのを眺めて祝う日です。今の感覚からすれば、グロテスクで悪趣味極まりないですが、この時代は、目の前で恐怖の原因が消し去られるのを確認することで、安らかな日常を取り戻すという現実的な意味を持っていたのです。
そして、同じ時代、こうした魔術的・類感的思考や盲信とは対極の方向にも社会は進んでいました。
1543年、ニコラス・コペルニクスの死の直前、彼の弟子であるゲオルク・レティクスがコペルニクスの手稿をまとめた『天球の回転について』が出版されました。それは、コペルニクスが長年の観測を元にした、地動説の緻密な体系を整理したものでした。コペルニクスを引き継ぐ形で、ティコ・ブラーエやヨハネス・ケプラー、そしてガリレオ・ガリレイが登場し、長年信じられてきた天動説は覆り、後の人類の宇宙開発にまで繋がる本格的な天文学が産声をあげたのです。
同じ1543年、アンドレアス・ヴェサリウスが著した『ファブリカ(人体の構造)』が発行されます。これは、豊富な解剖経験を元に、人体の構造を精密に描写した図版が多用された人体解剖図鑑で、骨格や筋肉だけでなく内臓や脳の構造まで明らかにされ、現代でも十分に資料として使えるものでした。この著作によって、解剖学が飛躍的に発展する基礎となっただけでなく、それまでの人体に対する宗教的な恐怖感などが払拭される契機ともなって、以降、医学や生理学の急速な発達をもたらします。
コペルニクスの時代から80年あまり下った頃、ヨーロッパでは魔女狩りの嵐が吹き荒れていました。1628年、ドイツのフランケン地方バンベルクの市長だったヨハネス・ユニウスは魔女のサバトに出席したとして告発され、処刑されました。男女、老若、そして社会的地位の区別すらなく、疑いをかけられたら最後、魔女や妖術師というレッテルを貼られて処刑されたのです。同じ年、イギリス人医師ウィリアム・ハーヴィは『動物における心臓と血液の運動に関する解剖学的研究』を発表し、循環器系の仕組みが明らかにされます。
こうした因習や盲信に囚われたままの反動と、科学的革新という両極が同居する社会について、イギリスの作家ポール・ニューマンは『恐怖の歴史』の中で、次のように分析しています。
「魔女迫害の絶頂期は、観察と実験の時代であるルネサンスの最盛期と重なっていた。魔女裁判はある意味で、科学的学問の普及に直面しての宗教による最後の抵抗と考えることもできる。…中略…つまり、学問の普及を前にしての、古いヘブライの一神教を復権しようとする最後の試みだったのである。迫害した者たちは誰も神の実在を肯定的に証明することができなかった。そのため、じつは迫害者たちは、サタン幻想を様々な『異邦人』や『疑わしい』男女に投影することで、後ろ向きの議論を行っていたのである。いいかえれば、魔女がいるのだから、魔女と徒党を組む悪魔も存在し、魔女と対立する神もまた存在する、というわけである」。
●革新と反動●
こうした、革新とそれに対する反動という構図は近代にも目立ちます。
18世紀中盤から19世紀にかけての産業革命の時代も、機械産業が発達し、医学や生物学、化学が新たな知見をもたらして社会を大きく変えていく一方で、多くの人々は混乱と戸惑いの中にありました。そして、中世同様の盲信に引き寄せられていきます。
1848年、ニューヨーク州ハイズヴィルのフォックス家で顕著な心霊現象が起こっていると報道されます。それはラップ音といわれるもので、一家の二人の姉妹が死者の霊と交信する能力を持ち、彼女たちの質問に、死霊がラップ音で答えるというのです。その話は、すぐに近所からハイズヴィル全体に知れ渡り、一気に全米に広まって熱狂的な関心を集めてゆきます。
マーガレットとキャサリンの姉妹は、舞台上でラップ音による死霊との交信を行い、全米を巡業しました。さらに、大西洋を越えてイギリス、ヨーロッパ大陸にまでその評判が広がり、姉妹はヨーロッパ各地も巡ります。これが契機となって、スピリチュアリズムが一大ブームとなりました。
欧米では、ヴィージャ盤による占いや霊媒が霊を降ろしてその霊をエクトプラズマとして口から出して交信するといったパフォーマンスが夜毎あちこちで行われるようになりました。また、学術的に心霊現象を研究しようという機運も高まり、あのシャーロック・ホームズシリーズの生みの親であるコナン・ドイルも加盟したイギリス心霊協会を嚆矢として、各国で心霊研究が盛んになっていきます。
そして、皮肉なことに、心霊研究の俎上に載せられた降霊術などの心霊現象は、ほとんどがトリックを使ったイカサマであることが露見してゆきました。
そんな中にあっても、フォックス姉妹の心霊現象は信憑性が高いように見えました。姉妹は巡業によって巨大な富を得ます。さらに、彼女たちを信奉する信者や支持者も増えていき、ピーク時には150万人に達したとも言われています。
しかし、彼女たちのラップ音もトリックであることが露見する日がきます。バッファロー薬科大学のチームが彼女たちのラップ音を詳細に分析してみると、それは指の骨を鳴らすように、関節で骨がこすれる音と極似していることがわかったのです。そして、実験の結果、足首と膝の関節の擦過音であると結論づけました。
この報告が出されると、姉妹はかんねんしてイカサマであったことを告白しました。体の関節を鳴らして遊んでいるうちに、足の関節を自由に鳴らして大きな音が出せるようになり、流行っていた降霊術と組み合わせて悪ふざけしているうちに、それが評判となって、ついには引っ込みがつかなくなってしまったということでした。
その告白は雑誌に掲載され、以降、姉妹は人前から姿を消しました。それでも彼女たちは本物であると頑なに信じる人たちも大勢いました。
19世紀最後の年の1900年、ドイツの科学者マックス・プランクが量子論を発表します。原子を分解してくと、量子という微小な粒となり、これがエネルギーを吸収し放射するというもので、物理学に大変革をもたらします。プランクに続いてアインシュタインやニールス・ボーアが量子力学を完成させると、それは技術文明のあり方そのものを大きく変えることになりました。
このプランクの量子論から15年後、ポルトガルの寒村ファティマである事件が起こります。
村の郊外のコーヴァ・ダ・イリアという牧草地で羊の番をしていた三人の子どもたちが、空に漂う白い人影を目撃しました。それは手も足もなく、「シーツにくるまれた人のよう」だったといいます。子どもたちはその夏の間に繰り返しその白い人影を目撃しました。夏も終わり近くなって、その人影は子どもたちがいた樫の木の下に降りてきました。そして、自分は聖母マリアだ名乗ったのです。さらに、二年後の10月13日に再びここに現れて重大な預言を人類に伝えると言い残して消えました。
子どもたちが、その体験を家に帰って話すと、村では大騒ぎになりました。元々カトリックの信仰が強い地方で、昔から聖母マリア降臨の伝説が伝わっていたからです。村の噂はまたたく間にポルトガル全土から、カトリック信仰が色濃いラテン諸国に広まりました。
そして、二年後の1917年10月13日、聖母マリアが降臨すると伝えたその日、牧草地は7万人の群衆で埋め尽くされていました。その日はどんよりとして雨が降っていて、群衆によって踏みしめられた牧草地は泥だらけでした。子どもたちは、その群衆をかき分けて聖母が現れると告げた樫の木の下までたどり着きました。
ここで祈りを捧げているうちに、子どもたちは衆人環視の元でトランス状態に陥りました。トランス状態にある間、子どもたちの目には降臨した聖母が見えていました。そして、秘密の予言を残すと、以前と同じようにスッと消えました。ところが、その間、周囲の人たちの目には、トランス状態になって身悶えしている子どもたちの姿しか映りませんでした。
子どもたちの姿が見えない、大多数の人たちは、何が起こっているのかまったくわからず、伝わってくるざわめきから、ただならぬ事態が起こっていることを想像していました。
子どもたちはがトランス状態を脱して立ち上がったとき、それまで空を埋め尽くしていた重い雲が割れて、そこから強い光が差し込んできました。子どもたちは、その方向を指差しました。それにつられて、群衆が空を見上げると、雲の切れ間から、太陽が顔を出しました。
太陽を見た群衆の誰からともなく叫び声が上がります。それにつられて、群衆の視線は太陽に釘付けになりました。彼らの目には、太陽が空中を「ダンス」するように、ジグザグに動き、円盤状に形を変えて地上に向かって降りて来るように見えました。また、太陽が空中でダンスしながら色とりどりのまばゆい光を放って見えたいう人たちもいました。そうした現象は10分あまり続き、気がつけば、再び雲が空を閉ざしていました。
これが「ファティマの奇跡(太陽の奇跡)」と呼ばれるものです。
今日では、それは、群集心理が生み出した集団ヒステリーの典型例として紹介されます。低温下で体が濡れ、泥濘んで不安定な場所に長時間立ち尽くし、疲労困憊していた中で、ようやく奇跡に出会えるという期待が最高潮に達したところに不意に光が指したことで、過敏になっていた神経が刺激されて幻覚を見たのです。さらに、周囲の人たちの興奮が坩堝となって、集団幻覚を助長しました。
こうした例は、まだまだたくさんあります。パンデミックのような全人類的な危機に陥ったとき、どうして人間の心理や社会は、このように二極化してしまうのでしょうか。今、世界を見渡してみても、まったく同じことが起こっています。そんな状況を見ていると、こうした二極化の矛盾といったものが、人間や社会の本質なのだろうかと考え込んでしまいます。
冒頭近くで、牧神が死んで、それがキリストに置き換わったという神話に触れました。それは、一神教がアニミズムに勝利して、人間が自然を支配する力を持った=自然に対する畏怖を捨てたということでした。ポール・ニューマンは、魔女裁判とはルネサンスという革新に対する一神教の最後の抵抗だったと分析しました。
牧神が死んだ後、一神教の神も死に、世界はルネサンスがもたらした革新と、それに続く技術革命を神の座に据えて突き進んできました。しかし、どんなに科学が進んでも、根源的な恐怖をもたらす疫病や災害は再び人類を襲い、人の心を中世の混迷に引き戻してしまう。
それでも革新は、新たな事態を乗り越えて進んでいきます。そして、人の心はそれに取り残されて、かえって退化していく……。革新と反動の二極化はますます大きく、そして深くなっていくように感じられてしまいます。こうした分裂は、いったい、この先、どんな社会をもたらすのか。分裂は埋まることがないのか。今回のパンデミックに直面して、そんな思いに囚われていました。そして、今回のような思索をしていきました。
過去を振り返り、そこに何かのヒントがないかと思って、様々な資料を参照して見つけたのが、先に挙げたポーランドの例です。ポーランドは、ヨーロッパに壊滅的な被害をもたらした中世初期のペスト禍に襲われながら、唯一ほとんど被害を受けませんでした。
ポーランドでは、まだ公衆衛生といった観念のなかった当時にあって、アルコール消毒が家庭で普通に実践されていました。そして、他の国々では農業革命が進展して、荒野が切り開かけて広大な農地が生み出されていく中で、手つかずの原生林が多く残っていました。そこは、まさに牧神が息づく世界、人と自然が共生する世界でした。
このポーランドの例は、はからずも革新の精神とともに自然と共生する社会こそが、理想的な社会であることを告げています。
今回の新型コロナウイルスも、元は野生に存在していたものです。人間が、野生を侵すことなく、うまく棲み分けができていたなら、人間界に登場して猛威を奮うこともなかったでしょう。
●あとがき的に●
今回は、21世紀に生きる私たちが初めて直面したパンデミックという事態の中で、いろいろと考えたことを書き連ねてみました。一刻も早く事態が打開することを願うとともに、これを貴重な教訓として、ここから学び、パンデミック後の社会のあり方を模索していかなければならないと思います。
◆バックナンバー購入ページ
https://www.mag2.com/archives/0001549333/
**参考**
『恐怖の歴史』(ポール・ニューマン著 田中雅志訳 三交社)
『狂気の歴史』(ミシェル・フーコー著 田村俶訳 新潮社)
>>>>>「聖地学講座メールマガジン」