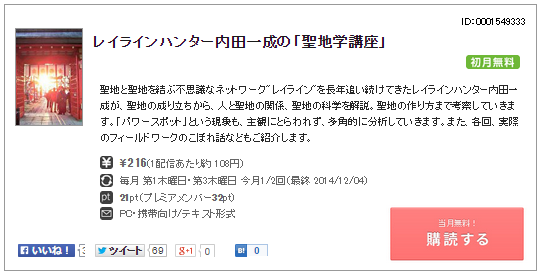未曾有の水害に見舞われた西日本の方々、心よりお見舞い申し上げます。また、亡くなられた方々のご冥福を深くお祈りいたします。
今回は、昨年の聖地学講座で取り上げた「錫杖を持った十一面観音」の全文を掲載します。
十一面観音は、通常、豊かな水の恵みの象徴であり、それに感謝する意味が込められた仏ですが、右手に錫杖を持った十一面観音が祀られている場所は、水害の危険地域であることを告げています。
繊細な自然観察を元に、それぞれの土地の気候風土やリスクなどを神仏を祀る形で残した古の人たち。そんな古の智慧を活かすことも防災におおいに役立つと思います。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
レイラインハンター内田一成の「聖地学講座」
vol.114
2017年3月16日号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
◯錫杖を持つ十一面観音
・錫杖を持つ十一面観音
・水害と十一面観音
◯お知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
錫杖を持つ十一面観音
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回の3月2日号の配信のとき、私はちょうど若狭で行われる「お水送り」の儀式に参加していました。この儀式についてはこの講座で何度も紹介していますので、あらためて解説はしませんが、私が参加するのも今年で12回目になりますが、毎回、雰囲気が異なり、またツアーに参加してくださる方たちもその都度異なって、新しい縁が生まれ、新鮮な気持ちで楽しんでいます。
ほんとうは、その後、12日に奈良東大寺二月堂で行われる「お水取り」にも行く予定だったのですが、外せない仕事ができてしまい、残念ながら参加がかないませんでした。
12日は、一緒に参加する予定だった人たちがフェイスブックに一日の行動をこまめにアップしてくれたので、それを見てせめてもの臨場感を味わっていました。その後、数日して、奈良のKさんからお水取り後に配布される「御香水(ごこうずい)」が送られてきて、若狭のお水送りの光景とみんながアップしてくれたお水取りの光景を思い出しながら、その透き通った聖水を飽きずに眺めています。
この御香水は、東大寺二月堂の本尊である十一面観音に捧げられるものと同じ水です。十一面観音は、北陸の名山・白山を開いた泰澄が白山の女神である白山比女(菊理姫)の本地仏として崇め、白山信仰とともに全国に十一面観音信仰が広がりました。今年は白山開山からちょうど1300年にあたり、泰澄が同じ時に開いた北陸の霊場では盛大な記念行事が行われます。
そんな記念すべき年でもあるので、今回は十一面観音をテーマにした記事にしようと思いバックナンバーを調べたところ、第6回『泰澄とその系譜』、第41回『水と聖地』、第94回『白山信仰の聖地と人』と計3回、すでに触れていました。十一面観音に特別な思い入れがあるわけではないはずなのですが、今回も思いつくというのは、やはりなにか心に響く存在なのでしょうね。
今回も十一面観音をテーマにするわけですが、過去の記事の繰り返しになっても意味がないので、今まで触れてきた泰澄や白山と十一面観音信仰という視点から離れて、もう一つの十一面観音信仰についてご紹介したいと思います。
【錫杖を持つ十一面観音】
一般的な十一面観音は、蓮華座の上に立ち、右手は垂下して数珠を持ち、左手には紅蓮を挿した水瓶を持っています。白山信仰に由来する十一面観音はこのスタイルで、水瓶が清らかな水とその慈しみを象徴し、数珠は衆生の幸福を願う姿を表しています。ところが、これと異なり、方形の大盤石の上に立ち、右手には錫杖を握り、左手に水瓶を携えた姿の十一面観音があります。
錫杖を持つものは、真言宗豊山派総本山長谷寺本尊の十一面観音像を代表として、ここから派生したものです。その由来から「長谷寺式十一面観音」と呼ばれます。
長谷寺の十一面観音は、朱鳥元年(686)に徳道上人によって造立されます。しかし、度々の大火によって焼失し、再造されてきました。現在の像は天文7年(1538)年に再興されたもので、像高三丈三尺六寸(1018cm)と木造仏としては我が国最大で、今でも鮮やかな金箔に覆われて堂内に浮かび上がる姿は迫力に満ちています。
数珠を持つ右手を垂下した一般的なスタイルの十一面観音の多くが、渓流の流れのようなすっきりとしたシルエットで、慈愛に満ちた優しげな表情をしているのに対し、この長谷寺の観音はたくましい体躯に太い指で力強く錫杖と水瓶を握り、その表情は強い意志を秘めてあたりを睥睨するかのような厳しいものです。
しかし、なぜ長谷寺式十一面観音は、数珠ではなく錫杖を持つのでしょうか。
白洲正子は『十一面観音巡礼』の中で、この長谷寺について次のように記しています。「おそらく長谷寺の元は、河上約半里の瀧蔵山にあり、いつの時か大嵐があって、神の岩座が転落し、その泊まった所が、「泊瀬(はつせ)」と呼ばれたのであろう。その川は、やがて三輪山を巻いて、大和平野をうるおす清流となるが、同時に「初瀬流れ」ともいって、しばしば荒れる恐ろしい淵瀬でもあった。そういう所が神の在す聖地として崇められたのは当然のことである。地形からいっても、三輪山の奥の院と呼ぶにふさわしい場所で、「こもりく」は神の籠る国を示したものに他ならない」
長谷寺のあるあたりは、かつて「泊瀬」もしくは「初瀬」と表記され「はつせ」と呼ばれていました。それが訛っていつしか「はせ」と呼ばれるようになり、「長谷」の字が当てはめられるようになりました。つまり、「長谷」はしばしば水害を起こす荒神が棲む場所だったわけです。
徳道上人は、この荒神を崇め祀って、その恐ろしい力を抑えるために、水神の化身(本地仏)である十一面観音を造営したのです。普通の十一面観音では荒神に対峙するにはか弱いため、力強い体躯と意志を持つ観音の姿とし、大地を鎮める法具である錫杖を持たせたのです。また、蓮華座ではなく方形の大盤石の上に立つのは、大盤石が地下の巨大な岩盤の一部であり、どんな水流にも負けず、そこに屹立し続けることを意味します。
白洲正子は、『こもりく 泊瀬』の中で、長谷寺の十一面観音が持つ錫杖について、さらに深く解釈しています。
「天満宮の石段の途中を右へ曲がると、「化粧坂」という峠があり、登って行くと、与喜浦に出る。ここが初瀬から伊勢へ通じる一番古い街道で、峠の手前に雲つくような巨巖がそびえて、泊瀬の斎宮跡と伝えている。『垂仁紀』にいう「磯城(しき)の巖樫本(いつかしのもと)で、倭姫はここに八年籠った後、伊勢へ向かわれた(倭姫世記)。初瀬の急流に面していて、いかにもそういう聖域にふさわしい地形である。……初瀬から少し登った小夫(おうぶ)の斎宮山にも、化粧川があり、そこの天神社には大来皇女(おおくのひめみこ)と、菅原道真を祀っているが、初瀬の周辺には道真と並んで、斎宮に関する伝説が多いのである。
天照大神と、十一面観音を、同体とみなす本地垂迹説は、おそらくこのあたりから発生したのだろう。岩の上に立ち、錫杖を持つ観世音が、天照大神の「御杖」となって、諸国を遍歴する斎宮の姿と重なったのは、自然なことのように思われる。が、長谷寺に十一面が祀られるまでには、長い年月がかかった」
長谷寺は、伊勢の斎宮跡と淡路島の伊勢の森を結ぶ通称「太陽の道」というラインの上にあります。そして、白洲が説明するように、この長谷から斎宮跡を通って伊勢へと抜ける街道は、もっとも古い伊勢街道です。
古代、この伊勢街道を通って、御杖代として天照大神を奉斎した倭姫が通ったのは間違いありません。崇神天皇の皇女豊鍬入姫が初めに御杖代となって、朝廷から天照大神を奉斎して旅に出てから、途中で倭姫に引き継ぎ、ようやく伊勢に落ち着くまでに80年の月日がかかりました。その途中、泊瀬=長谷のあたりにしばらく留まり、それが「斎宮」の地名として残っているのです。そんな斎宮の記憶が、後に錫杖を持つ十一面観音の姿として習合していると白洲は考えたわけです。
長谷寺から伊勢街道をさらに東に進んで三重県に入ったところに、「太郎生(たろうお)」という集落があります。この住民は、古代に御杖代である倭姫を先導した日置氏の末裔だという伝承を伝えています。おそらく、彼らのように長谷寺付近にも、街道の守り人として残留した人たちがいたでしょうから、彼らが御杖を手に黙々と旅する倭姫=斎宮のイメージを錫杖を持つ十一面観音に仮託したとも考えられます。
【水害と十一面観音】
畑中章宏は、『津波と観音 十一の顔を持つ水辺の記念碑』の中で、先にあげた白洲の文章や、柳田国男の著作、さらに西郷信綱の『古代人と夢』などを引用しながら、長谷寺式十一面観音の全国の所在地を紹介しています。ここでその全てをあげることはできませんが、いくつか畑中の著作から拾ってみると、鎌倉長谷寺、伊勢近くの丹生山長谷寺、神奈川県厚木市の飯上山長谷寺(いいかみさんちょうこくじ)、長野県篠ノ井の金峯山長谷寺(きんぽうざんはせでら)、岐阜県羽島市の中観音堂などがあります。
長谷寺式十一面観音が祀られている場所は川の氾濫があったり、あるいは津波被害があった場所であることが多く、錫杖を持って大地と水を鎮めるその姿に一致します。羽島市の中観音堂に安置された十一面観音は、円空作と伝えられています。円空は、幼いときに母親を水害で亡くし、その後母の菩提を弔うために、全国を行脚して十二万体の仏像を刻んだと伝えられますが、彼が故郷に近いこの地に錫杖を持った十一面観音を祀ったことの意味はとても深いといえるでしょう。
畑中章宏は『災害と妖怪 柳田国男と歩く日本の天変地異』では、柳田国男が各地から収集した妖怪譚の内容を災害史の観点から分析し、フォークロアとして残された災害の記憶を丹念に掘り起こしています。この2月に出版された『天災と日本人: 地震・洪水・噴火の民俗学』(ちくま新書)では、より具体的な観点からフォークロアと災害の関連性に焦点を当てて、「災害民俗学」と呼べるような分野を立ち上げました。
今回の記事は、彼の著作を参考にさせていただきました。
信仰を、ただ宗教史的側面から捉えるだけでなく、信仰の原点が災害のような「リアルな体験」を下敷きにしているものだと捉えることで、また新しい展望が開けてきます。
それは、「災害の時代」に入った今、もっとも必要な視点といえると思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━