縁あって、那須の二期倶楽部が主催する 『山のシューレ』で樹と触れ合うツリーイングのプログラムをイベントの一つに加えていただいた。
『山のシューレ』は、那須のリゾート関連施設が合同で行う『アート・フェスタ・那須』 の一翼を担うイベントでもあって、その中では、各プログラムの講師がアート・フェスタ・那須のテーマである「言葉、身体、環境」 に因んだ推薦図書を挙げて、それにコメントするという企画がある。
選ばれた本とコメントは、アート・フェスタ・那須に参画する施設と東京・九段にあるギャラリー『冊』で、巡回展示されるのだという。
さて、何を選ぼうかと思い、まず環境のテーマでは、レイチェル・カーソンの『センスオブワンダー』 を選択した。
レイチェル・カーソンといえば、今の環境保護運動の源流ともいえる『沈黙の春』があまりにも有名だが、 彼女は幼い頃から自然と親しみ、自然が湛える「ワンダー」を常に感じていて、それが損なわれていくことに深い悲しみを覚えたことが 『沈黙の春』を著す原動力になったといえる。『センスオブワンダー』は、彼女が孤児となってしまった姪の息子を引き取り、 一緒に身近な自然に触れていく過程を著したもので、未完のまま彼女が亡くなり、その草稿をまとめて出版されたものだ。小品だが、 姪の息子ロジャーがカーソンに見守られながら、身近な自然に「ワンダー」を見いだしていく姿が、心に染みてくる。『センスオブワンダー』 を読めば、そこに記された精神が『沈黙の春』のまぎれもまい源流であることが理解できる。そこで、これを環境というテーマに入れてみた。
さらに、言葉というテーマでは、『遠野物語』を選んだ。
もともと農山村の景色は、日本人の死生観や自然観をそのまま物語る「言語」だったという気がしている。 神々や魑魅魍魎の住処である山、人々が安全に暮らせる場である里、その山と里との境界で、人は神や魔と出会い、物語が生まれる。 そんな物語を詩的に表したのが遠野物語だった。
今では、神や魔の住む世界と人間の世界が混交してしまい、安全で心安らぐ「里」に当たる人間世界は崩壊してしまっている。今いちど、 人が助け合って安心して暮らせる本来の「里」を取り戻すためには、遠野物語は最適なテキストになるのではないか、 そこに記述されている風景を言葉として読み取ることで、現代人が忘れてしまったものを思い出すことができるのではないかと思ったのだ。
身体というテーマでは、いろいろ迷った挙げ句、多田富雄氏の『生命の意味論』を選んだ。じつは、「身体」というテーマで、真っ先に 『生命の意味論』とこの著作の双子のセットともいえる『免疫の意味論』が思い浮かんだのだが、 両書ともその取っ掛かりは身体を構成する細胞から話が展開していくのだけれど、そこからすぐに免疫系という観点から見た「自己」と「非自己」 の話になり、いったい生命とは何かというところへ話が進んでいく。それでは、身体=ボディというイメージから、 離れていってしまうように感じた。
だが、単純にボディワークの本でも面白くないし、逆説的に、 身体活動を極限まで沈静化していった地平にある禅の本でも挙げてみようかとも思ったが、それもなんだかあざといようで……と、堂々巡りして、 結局、『生命の意味論』に落ち着いた。
生命は、その生命がどのような形になり、どのような生を歩んでいくか、ブループリントのようにあらかじめDNAに記述されている…… そうした還元主義的な見方に対して、多田氏は免疫系システムや体細胞の分化を例に、生命系はじつはかなりあいまいなシステムで、 自己組織化してできあがっていくのが個々の生命であり身体であると解く。さらに、発達過程に適度なあいまいさが含まれているからこそ、 進化もあるのだと。
個々バラバラなファクターが働きつつも、相互作用から「偶然」今の自分たちの身体ができあがっていると言われても、はじめは、 なんだかピンとこないが、自分が生きていることで、様々な外的状況に出くわし、いうなれば「場当たり的」に対処してきた結果が、 今の自分が置かれた立場であり、自分の身体状況だということを考えれば妙に納得がいく。
多田氏は、専門の分子生物学から玄人はだしの能の世界を例にとって、同じ「生命」 というテーマをわかりやすい比喩を交えて解説してくれるので、ぼくのような文系の人間にも概念が飲み込みやすい。
都市や国家、官僚制といった社会システムも、個々バラバラなファクターが相互作用して自己組織化していく生物の「身体」 とそっくりなスーパーシステムなのだといったあたりは、まさにリヴァイアサンの「身体」構造を説明しているといえる。
そんなわけで、三つのテーマに対応した三冊の本は選べたのだが、今度は、 これにコンパクトで気の利いたコメントを付けなければならない……。


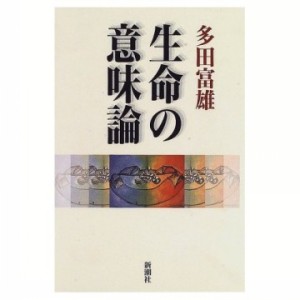




コメント