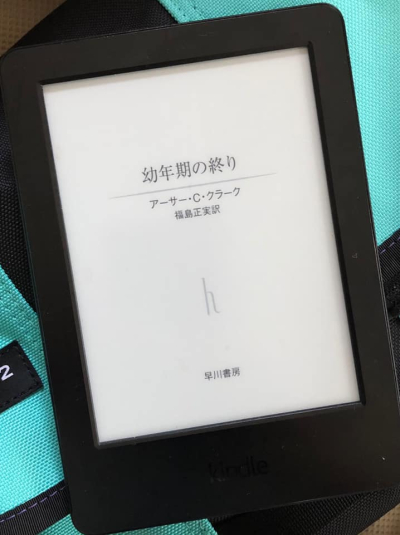
コロナ禍が世界を覆いはじめて以降、古典というか、準古典というか、20世紀中葉の頃の著作を読み返している。
ハクスリーの『素晴らしい新世界』、レヴィ=ストロース『野生の思考』、フーコー『狂気の歴史』、マルクーゼ『一次元的人間』、バーリン『自由論』、そしてアーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』…。
どれもみな20代のはじめに読んだもので、中には何度も読み返しているものもある。
この頃のこうした著作は、世界大戦という巨大な災禍の経験によって、人間とは何か? その行末はどうなるのか? という問題を文字通り突きつけられ、戦後の急速に変わってゆく世界を見つめながら、深く考察して著されたものだ。
そこには、今にはない、地に足がついたというか、安定した思想基盤を持って見据えられたビジョンがある。
ポストコロナの社会がどうなるのか、人の意識はどう変わるのか、今、いろんな見解が提示されているけれど、どれもこれも、皮相でただの希望的観測や根拠のない理想論でしかない。
クラークの『幼年期の終わり』では、数百万年の人類の進化の果て、リニアな「進化」ではなく、遷移を遂げる。それは、リニアな進化のベクトルに乗ってきた既存の「人類」にとってはデッドエンドだったわけだけれど、そもそも宇宙の原理とは、人間的な「情」とは無関係なものだと主張している。「2001年宇宙の旅」のテーマも意識の進化(遷移)だった。
ある日突然、それまでの価値観が全て吹き飛ぶような事態も起こる。コロナ禍はまさにそういうエポックになる可能性がある。
最近、人類学研究から、人類は7万年前に突然「意識」を獲得したのではないかという説が発表された。
ホモ・サピエンスが想像力を持つようになり、同じ種が協調して暮らすようになったことが、非力な動物から地上の覇者への転換点だったという理論が、以前からあった(ハラリの『サピエンス全史』は、まさにそれを主題としている)。
しかし、ホモ・サピエンスが想像力…意識と言い換えてもいい…を持つようになったきっかけは不明で、それは「コンシャスネス・インフラックス」あるいは「スピリチュアル・インフラックス」としか喩えようがないイヴェントだった。
7万年前の意識の芽生えの痕跡の発見は、まさに、そういうインフラックスが現実に起こったことを証明するのかもしれない。
もしかすると、ポストコロナで人類が経験するのは、そういったことに匹敵するようなイヴェントになるのかもしれない。
そして、それはある意味、今、当たり前だと思っている「情」から見れば、「無情」「非情」なものになるかもしれない。
人の思いがどうあろうと、変わるときは変わるし、その変化を受け入れるしかない。
今はそんな瞬間なのかもしれないという予感とともに、それがどんな世界になるのか想像するためのテキストとして、また、その衝撃に備えるために、こうした先人たちの深い考察に触れておくことが大切ではないかと思う。




コメント